最近、「生徒数の足りない大学、いわゆる〇ランク大学」と呼ばれるような大学が、障がいのある学生を積極的に受け入れているという話を耳にしました。これは一見とても前向きなニュースのようにも思えますが、本当にそれで良いのかどうか、よく考えてみる必要があるのではないでしょうか。
「インクルーシブ教育」という言葉は今やよく耳にします。みんなが一緒に学び、働く社会を目指すという理念。とても理想的だし、すばらしい目標だと思います。でも、現実を見ると、それが本当にすべての人にとって幸せなのか?と疑問に思う場面もあります。
全ての人が「同じ空間」で学ぶことが、本当に「同じように」学べるということではありません。支援の形も違えば、必要な環境も違う。そこを無理にひとくくりにしてしまっては、逆に誰かを苦しめることにもなりかねません。
そして何より、日本社会全体が「違う人」を受け入れる心の準備ができているのか、正直まだまだ難しい気がします。自分とは違う背景、違う特性を持った人を自然に尊重すること、それが当たり前の文化として根づいていないと、インクルーシブの本当の意味には近づけないんじゃないかと。
特に気になるのは、大人たちがその本質をしっかり理解しないまま、「じゃあ学生の皆さん、インクルーシブよろしく!」と丸投げしてしまうケースです。理解も準備もないまま現場に任せてしまうのは、どう考えても無責任に感じます。
インクルーシブ教育の意義は、単なる「共存」ではなく「相互理解」にあります。見た目の整合性を保つのではなく、心のつながりをどう築いていけるか。そのためには、制度や環境づくりと同じくらい、私たち一人ひとりの「受け入れる力」を育てることが大切なのではないでしょうか。

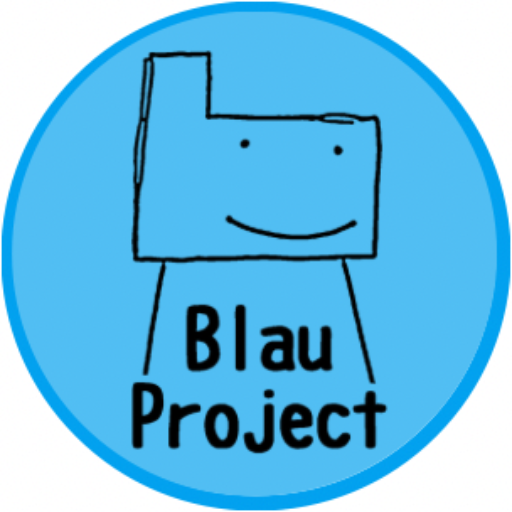

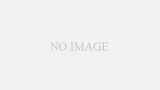

コメント